6月2日、「第5回尊皇倒幕のバイブル、靖献遺言を読む会」を大手町で開催した。今回は『靖献遺言』「諸葛亮」の続きと「陶潜」の項を読んだ。
浅見絅斎は『靖献遺言』に「諸葛亮」を収めるにあたり、「三国志演義」等で有名な諸葛孔明の軍略智謀をあえて述べず、「出師表」を掲げ諸葛亮が「謹慎の人」であることを示した。「謹慎の人」というのはどういう感覚かは現代人にはわかりづらいが、道義を再興し、君たるべき人につかえることで乱世を鎮めようという精神である。諸葛亮にこの「謹慎」の精神があることを指摘したのは水戸学の藤田幽谷であった。
「陶潜」は陶淵明の名で現代日本人にも知られている、漢詩人として有名な人物である。陶潜は西晋につかえていたが、その崩壊とともに隠棲し、二度と出仕しなかった。陶潜は、殷が滅亡して周が成立した後も殷への忠誠を忘れず餓死した伯夷・叔斉に心を寄せていた。それは、陶潜の名作とされる「帰去来の辞」にも窺うことができる。陶潜は、燕のために秦王を暗殺しようとした荊軻たらんとする志を秘めていたのである。
《志士の名言:陶潜編》
◎「かの天命を楽しみ復たなにを疑わん」〔天から与えられた使命のままに安んじて、何の疑うところもないのである。〕
次回は文天祥を輪読する。〔小野耕資〕

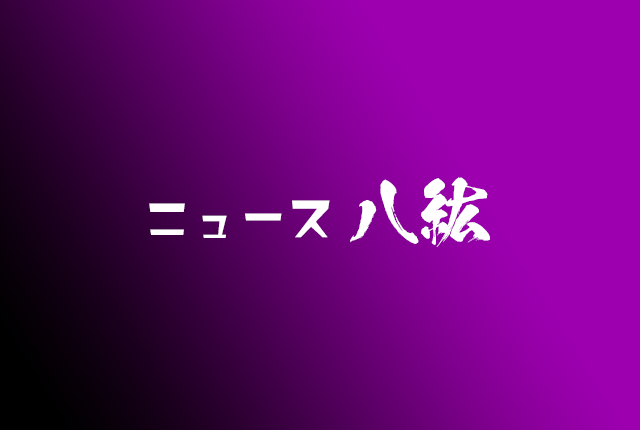
.png)
.png)



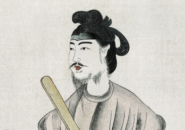





.png)
.png)
.png)




