6月2日、愛知県岡崎市六ツ美地区にて第104回六ツ美悠紀斎田お田植えまつりが催された。これは、大正天皇の大嘗祭で用いられる新米を耕す斎田に当地(碧海郡六ツ美村)が亀卜で選ばれた事を記念するもの。実に一世紀以上にわたって開催されており、100周年記念となる平成27年には秋篠宮殿下・同妃殿下の御高覧にも預かった郷土の誉れである。
当日は、まず、斎田準備中に寄り合い場所として多用された歴史を持つ中島八幡社へ。当社は全国的にも珍しい大正天皇を祀る大正宮があり、耕作に使用された道具を保管する倉庫も見られる。
続いて、お田植えまつり会場である岡崎市地域交流センター六ツ美分館・悠紀の里へ。こちらには斎田のみならず、当地を流れる矢作川周辺の稲作文化の歴史を紹介する資料館もあり、当日はJR東海の主催する「さわやかウォーキングの経由地になっていた事もあり、多くの参加者が展示を興味深く見ていた。施設前の広場では地元有志による上演が催され、賑わいを見せていた。午後、は地元中学校の吹奏楽演奏や保存会による神楽舞が披露された後、斎田前にて厳粛に神事が執り行われた。また、斎田は京都より東のものを悠紀(ゆき)、西のものを主基(すき)と呼ばれるが、大正期に悠紀斎田とされた六ッ美村と対となる主基斎田に香川県綾歌郡綾川町の地が選ばれた事が縁となり、神事には岡崎市の市議会議員のみならず綾川町の関係者も多く出席されていた。神事の後、当時のままの衣装や作法によるお田植えが披露された。前後して、当日の夕刻に大正期に悠紀・主基に選ばれた岡崎市・綾川町の両自治体が正式に交流提携の調印がなされる旨が発表された。折しも、当日は全国植樹祭に御出席なされるべく天皇陛下が愛知県にお出ましになり、御代変わりで宮中儀式に関心が高まる中で意義深き一日となった。
なお、大正期の悠紀斎田に関する詳細情報は『国体文化』誌上で改めて筆を執りたい。
〔三浦充喜〕
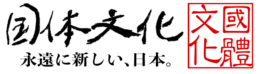

.png)
.png)


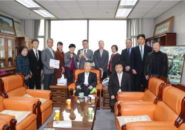









.png)
.png)
.png)




