平成31年3月9日午後、貸会議室オフィスゴコマチ(京都市)にて、民族文化研究会関西地区第11回定例研究会が開催された。
報告者は、中村龍一氏と湯原静雄氏。
まず、中村氏が、「日本音樂を私達の生活に取り戻すために(第八囘) ― 三味線音樂」と題し、地歌・長唄・浄瑠璃といった三味線を使用した音楽・歌劇の歴史的沿革を概観した。三味線は、近世以降の日本音楽では非常に広範囲で使用される楽器であり、三味線への理解は日本音楽史を把握するうえで極めて重要である。

小野清一郎
続いて、湯原氏が、「小野清一郎の刑法思想 ― 仏教教学からの影響を中心として」と題し、近代日本刑法学の中心人物だった小野清一郎の刑法思想を、仏教から受けた影響を中心として概観した。小野は、新派・旧派論争をはじめとした近代西欧の刑法理論が陥った理論的閉塞を、日本思想なかんずく仏教思想の見地から克服しようと企図する。この報告では、こうした小野の企図に焦点を当て、西欧の近代的社会科学と日本の民族固有文化のあいだで、いかなる対話や統合が可能かを考察した。
今回も活発な議論が展開された。
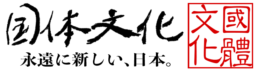
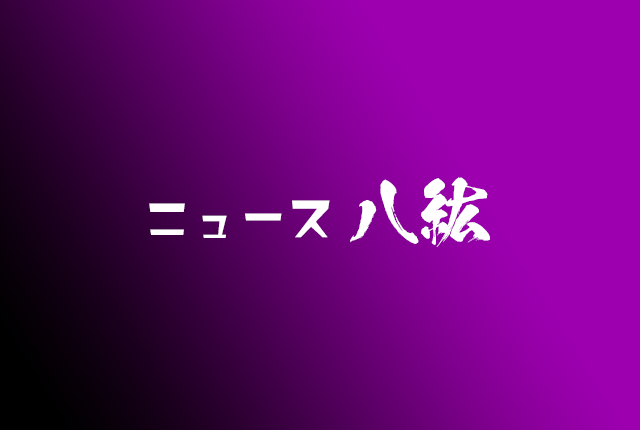
.png)
.png)



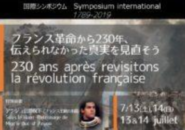
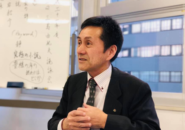





.png)
.png)
.png)




