10月18日午後、《崎門学研究会》特別講座・第一回「天皇親政を考える勉強会」が開催された。
まず、浅草・海禅寺に建つ梅田雲浜の墓所で、折本代表が雲浜の『訣別』を奉吟。幕末の志士で、安政の大獄で処刑された梅田は、崎門派の流れを汲む。
その後、上野の会議室で勉強会を実施。折本代表を報告者として、親政に関する議論を学んだ。以下要約。
今日における天皇を巡る代表的な議論としては、①天皇不要論、②天皇機関説・象徴天皇論、③天皇親政論、という三つを挙げることができよう。そのうち、①と③は少数で、ほとんどが②に含まれる。天皇は実権を持たないという②は、「君臨すれども統治せず」という英国王室流のスタイルとして広まった。一方、③を目指す学問である崎門学は、その意味において日本の正統を護ろうとする主張だ。天皇親政とは、天皇独裁・天皇専制とは異なり、純粋に公的な存在である天皇が民の意見を御嘉納されて重要な政治決断を行う「民中心の政治」である。
その意味における「天皇親政」が実現した時期は短いが、目指すべき理想として常に意識されてきた。明治維新に際しても「天皇親政」が謳われたものの、大久保利通や伊藤博文といった藩閥政治家に牛耳られて天皇の存在は棚上げされてしまったため、「天皇親政」論に基づく現実政治批判が現れる。紀尾井坂の変で斃された大久保利通の斬奸状における有司専制批判や、伊藤博文らに抗すべく「教学大旨」を起草した元田永孚らの動きなどは、その代表的事例であり、後者の活動は「教育勅語」に結実する。また、大日本帝国憲法の制定過程では、②を目指す伊藤に対して③を目指す井上毅が抵抗を試み、③の要素も取り込まれたが玉虫色の内容となった。
大東亜戦争敗戦後、そのことを徳富蘇峰は日記の中で問題視している。蘇峰は、昭和天皇を冒瀆する意図はないと断りながらも、昭和天皇が英国流の教育を受けられ、英国王室流の国政の関与をされたことを不満とし、周囲の人間の教育に問題があったのではないかと述べた上で、「皇室中心主義」を掲げ、政治機構の中心に皇室が立つべきことを主張するのである。
天皇親政論に対して「天皇が一人で政治総てを見ることはできない」という批判が存在する。これは当然の指摘だ。しかし、「皇室が中心にいる」ということを常に確認しなければ政治実務者の専横を抑止することは不可能だ。
次回もまた天皇親政に関する勉強会を行う。〔愚泥〕
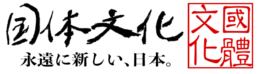
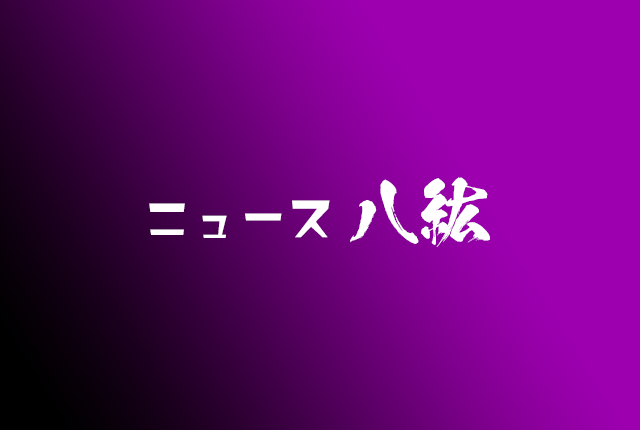
.png)
.png)



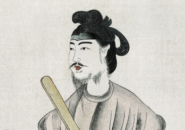




.png)
.png)
.png)




