明治維新から150年にあたる本年、維新を象徴する人物の一人・西郷隆盛に関する講演会が各地で開かれている。

西郷の今日的意義を説く金子編集長(提供:宗教新聞社)
11月15日午後、アルカディア市ヶ谷(東京都新宿区)にて宗教新聞社の主催により、金子編集長が「征韓論から西南戦争へ、西郷の理想と現実」と題して講演し、約50名が聴講した。
征韓論の経緯を紐解いた金子編集長は、自ら全権大使として乗り込もうとした西郷の心事について、「正道を踏み国を以て斃るゝの精神無くば、外国交際は全かる可からず」という『南洲翁遺訓』と相通ずるものであることを認めつつも、調整型政治家であったはずの西郷が政治的根回しを怠ったために唐突な印象を与えると指摘。
また、西南戦争についても、どうして他の士族反乱に呼応しなかったのか、そもそも蹶起の意思があったのか、さらには熊本城攻略に拘泥したのは何故か、など様々な謎があると述べた。
西郷を巡る史実と物語を振り返った金子編集長は、生涯を貫くものとして「道義」を見出し、その再評価のみならず実践の重要性を強調して講演を結んだ。
本講演については、宗教新聞社ウェブサイトで詳報されている。

金子編集長の講義に聞き入る聴衆(提供:姫路獨協大学)
11月17日午後、姫路獨協大学(兵庫県姫路市)で同大学播磨会主催の《はりま歴史講座》が開催され、金子編集長が「未完の明治維新―象徴としての西郷隆盛」と題して講演した。
明治維新に対する後世の評価を①「近代市民革命」・②「復古即革新」・③「近代資本制国家形成」・④「絶対君主制国家形成」・⑤「大義なき権力簒奪」の五つに大別した金子編集長は、②を象徴する人物として西郷を挙げた。こうした西郷観は、明治国家が推し進めた近代化政策に対する違和感を反映しているとした金子編集長は、葦津珍彦・影山正治・内村鑑三・山本七平・田中智學の西郷論を紹介し、彼らが絶対的存在としての「天」、ひいては、その意思にして絶対的軌範としての「道」を意識していたことを指摘。
さらに、葦津・影山・田中は「天」の意思を継承し、「道」を体現する神聖者としての天皇を尊崇し、そうした天皇の御存在を現実政治に反映させるべく「第二維新」を志向していたことに言及した。こうした観点からすれば、「明治維新」は未完である。また、近代化に対する疑念は、全てが相対主義的になり、交換可能性を示す金銭の多寡が価値を判断する基準となってしまった現代日本に対する警鐘としての意義も有すると結んだ。〔M・K〕
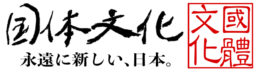
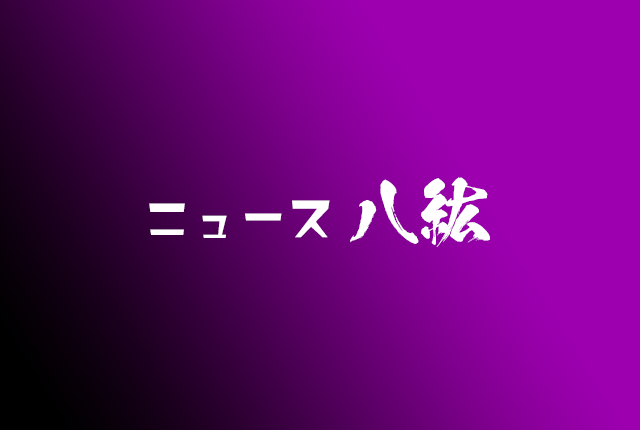
.png)
.png)

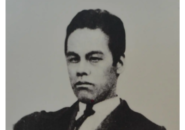









.png)
.png)
.png)




