2月11日は、神武天皇による肇国を奉祝する「紀元節」である。敗戦後の占領下に廃止されたものの、昭和41年に「建国記念の日」として復活した。祝日法に日付が明記されていない、政府主催の奉祝行事が行われていないなど幾つかの問題点はあるが、全国各地で民間有志による奉祝行事が以下のように行われている。
2月11日16時から、星陵会館(東京都千代田区)にて、第35回「紀元節奉祝式典」が開催された。
皇居遥拝・橿原神宮遥拝・国歌斉唱に引き続いて、斎主・高橋宏篤氏、祭員・櫻井颯氏、典儀・若瀬颯仁氏により紀元節祭を斎行。修祓の儀・降神の儀・献饌の儀・祝詞奏上・神武天皇即位建都の大詔奉読・橿原神宮扇舞奉納・紀元節の歌奉唱・玉串奉奠・撤饌の儀・昇神の儀・斎主祭員退下の順に行われ、終了後に桑木野義郎実行委員長から主催者挨拶があった。
休憩後、宮本雅史氏(産経新聞編集委員)による「昭和から平成、そして新しい時代に~連綿と続く大御心に感謝」と題する記念講演。パラオ共和国の元コロール州酋長だったイナボ・イナボ氏(故人)が、平成7年8月15日に靖国神社で行われた戦没者追悼中央国民集会に参加した際、「日本の大切なものが四つあり、天皇陛下・靖国神社・富士山・桜である。パラオは日本人から〔勉強・修身・男であること・責任を持つ・約束は守る〕ということを教わった」と雑誌のインタビューに答えたことを引き、こうした発言により「日本の心」を呼び起こされると同時に、日本人であることの誇りを実感すると述べた宮本氏は、パラオから気付かされたことを肝に銘じ、皇室をお守りし、日本人としての誇りを忘れず新時代を迎えたいと締めくくった。
講演終了後、富田安紀子氏により決議が朗読され、拍手多数により採択。最後に、玉川博己氏の先導により聖寿万歳が行われた。
採択した決議の文中には「本年は皇紀二千六百七十九年である。我らは(中略)皇紀二千七百年が国家行事として慶賀奉祝されることを目指し奮励努力する」という一節がある。この決議は、後日、内閣府と自民党本部に手交したそうだが、国の誕生日である紀元節は「国家行事」として奉祝されるべきであろう。〔田口仁〕
2月12日、岐阜市文化センターにおいて、天皇陛下御即位三十年岐阜県民奉祝準備委員会および建国記念の日を祝う県民の会主催の「奉祝 天皇陛下御即位三十年 建国記念の日を祝う県民のつどい」が開催された。
当日は生憎の小雨であったが、多くの参加者が訪れ、定員約500名の会場で立ち見も出るほどであった。
式典は開会の辞の後、神武天皇陵を遥拝。国歌斉唱、主催者式辞に引続き、来賓の挨拶。《明治の日を実現する議員連盟》の会長として精力的に活動されている古屋圭司衆議院議員や松井聡羽島市長を始め、岐阜市議会議員や岐阜県議会議員から挨拶があった。その内容も多岐に渡ったが、特に「建国の由来」との関連で「教育」が取り上げられていた。次いで、野田聖子衆議院議員などからの祝電が披露された。
記念講演は、京都産業大学名誉教授の所功氏。「新しい皇室と元号への展望」と題して、御代替わりに伴って改められる元号について、次世代における元号の在り方について、歴史的経緯を踏まえつつユーモアも交え、大変分かり易い説明をされた。また、菊の御紋と羽島市の美濃菊との繋がりや関市(旧武儀町)平成地区に関する言及など、岐阜県と皇室との関わりにも触れられ、非常に興味深いものであった。また、ご自身の経験を交えながら、御代がわりに備えた各メディアの動向についても言及があった。
記念講演の終了後に、奉祝歌の斉唱、聖寿万歳が行われ、滞りなく式典は幕を閉じた。〔三浦充基〕
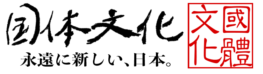
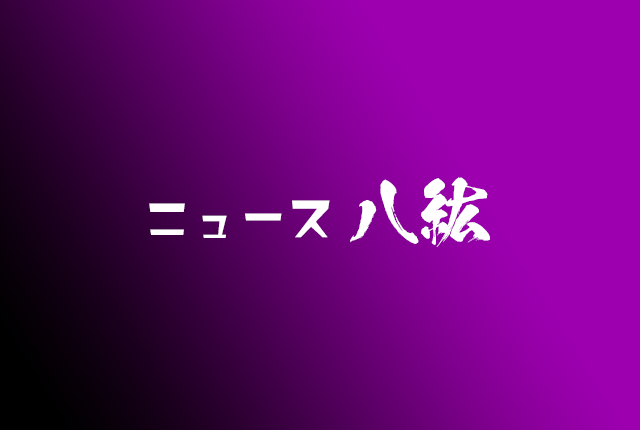
.png)
.png)





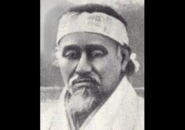





.png)
.png)
.png)




