11月25日午後、東京都内の星陵会館大ホールにて、歿後四十九年目の三島由紀夫追悼の集い「憂国忌」が開催された。総合司会は佐波優子氏。18時からの黙祷に始まり、三島由紀夫研究会代表幹事・玉川博己氏による開会の辞に続き、シンポジウムが催された。テーマは「三島由紀夫の天皇論」。進行役を三島由紀夫研究会事務局長・菅谷誠一郞氏が務め、作家・文藝評論家の藤野博氏、里見日本文化研究所の金子宗德所長、展転社の荒岩宏奨代表取締役が登壇。
藤野氏は「二・二六事件と私」を通じて、三島が「天皇制」を「戦前と戦後をつなぐ岩盤」として見出していたことを提起。三島は青年時代、父から兵役逃れを入り知恵されながらも検査を通過。結局、肺病と誤診され、戦時中は招集を免れてしまうわけだが、そうした複雑な心境からその思想的出発点を探る。かつ「人間宣言」への誤解を根本から解きほぐし、帝国憲法の「神聖不可侵」の底流に古来の祭祀者としての天皇の「神格性」を見出すなど、単なる「戦前回帰」には留まらない三島の国体論の本質を語った。
金子氏は 御代替わりに伴う大嘗祭までの一連の宮中行事を冷静に分析。今日の社会不安の背景に近代科学や資本主義、個人主義の存在があることを認め、そこから個人を超える究極的な価値を説く宗教の必要性を再提起。その中で、今こそ日本的な「多神教」概念に止まらない、「一神教」をも含んだ三島の天皇論が不可欠であることを強調した。
長年、皇室行事での国旗配りの奉仕活動に従事してきた荒岩氏は、昨今の即位礼のパレードにおける参列者の〝スマホかざし〟への違和感を隠さない。「週刊誌的天皇制」が愈々顕在化している現在の状況を憂え、三島の「文化概念としての天皇」を日本武尊以来の日本神話の「神人分離」まで遡った。その上で、保田與重郎を始めとする日本浪曼派の系譜につながる本質な天皇論を説き起こした。
討議終了後、参議院議員の中西哲氏、文藝評論家の富岡幸一郎氏による追悼挨拶があり、三島の天皇論を総括。その遺志を継承しつつ、安倍政権が長期化する中での憲法改正の機運が改めて表明された。
今回のシンポジウムでは、天皇論や国体思想に一家言のある論者を集めることで、濃密な討議が実現できた。とりわけ楯の会事件を直接知らない世代も交えることで、従来の作家論や作品批評に留まらない、形而上学的な内容を含んだ三島論にまでに発展。来年の歿後五十年へと繋いでいく上でも、大きな思想的転回を示した。〔山本直人〕
なお、本シンポジウムの概要は「国体学者・金子宗徳公式ウェブサイト」に掲載されています。
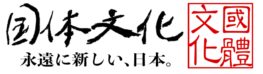

.png)
.png)

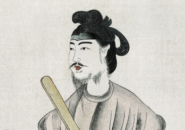


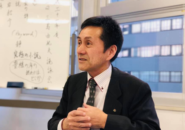





.png)
.png)
.png)




