この記事は【「国体」の語をもてあそぶな!白井聡氏の『国体論 菊と星条旗』を斬る(前編)】の続きです。
先日、白井氏は『国体論 菊と星条旗』という新著を刊行した。
白井氏によれば、同書は「国体」を機軸として、明治維新から現在に至るまでの近現代日本史を把握することを試みたものとされる。
白井氏によれば、「戦前の国体」とは「万世一系の天皇を頂点に戴いた『君臣相睦み合う家族国家』を理念として全国民に強制する体制」である。
そして、この「体制」は反対者・批判者を圧殺して破滅的戦争に踏み出し、内外に膨大な犠牲者を出した挙句に崩壊した。
けれども、「アメリカ(マッカーサー)を日本の天皇より構造的に上位に置く形」に「国体」はフルモデルチェンジされ、かかる「戦後の国体」は今日に到るまで継続している。
そこにおいては、
(1)「万世一系の皇統」に代わる「日米同盟の永遠性」が重視され、
(2)「祭政一致」における神官の役割はグローバリズムを礼賛する経済専門家たちに取って代わられ、
(3)「八紘一宇」は「パックス・アメリカーナ」に方向性を転じ、
(4)「文明開化」は「アメリカニズムへの追随」へと姿を変えた。
そして、国民を再び破滅に追い込もうとしているという。
見かけだけの斬新さ
敗戦後においても「国体」は形を変えて継続しており、戦前の歴史を繰り返しているに過ぎないという主張は一見すると斬新である。
さらに、様々な文献を持ち出しながら畳み掛ける手法も相まって、「意識の高い」読者のプライドをくすぐるが、 仔細に読んでみると幾つかの問題点が存在する。
第一に、「戦前の国体」に対する「万世一系の天皇を頂点に戴いた『君臣相睦み合う家族国家』を理念として全国民に強制する体制」という評価についてだ。
「全国民に強制する」というが、いったい何をもって「強制」とするのか。
「君臣相睦み合う家族国家」という観念じたいは明治期の井上哲次郎あたりを出発点とするものの、政府が「家族国家」論を強調するようになったのは天皇機関説問題を受けて昭和10(1935)年に「国体明徴声明」を発して以降のことだ。
いわゆる「国家神道」に関する島薗進氏の議論にもいえることだが、様々な社会システムを通じて国民に広く受け入れられているという事実と政治権力の発動とを混同してはならない。
読み手を惑わす白井氏
第二に、「フルモデルチェンジ」という評価についてだ。
この語は、主として自動車業界において用いられるもので、愛称は維持しつつも装備(エンジンやデザイン)を一新することだが、これは商業戦略における手段であり、それを「国体」という概念に当てはめることが適切か?
それで構わぬというなら、「国体」は内実のない虚名に過ぎなくなり、どうして「全国民に強制する」力を有したのか説明できない。
何故、これらの問題が生じるのかといえば、「国体」に対する精確な定義を欠いているためだ。
白井氏は、「『国体』が戦前日本と戦後日本を貫通する『何か』を指し示しうる概念である」と記すだけで、その「何か」の内実を明示しようとしない。
それどころか、先に見た通り、「万世一系の天皇を頂点に戴いた『君臣相睦み合う家族国家』を理念として全国民に強制する体制」と記す一方で、国体の破壊(敗北と被支配)は国体の護持(天皇制の堅持)であり、国体の護持(君主制の維持)は国体の破壊(民主制の導入) であった」とも記す。
内実を敢えて曖昧にすることで、 白井氏は読み手を幻惑している。
安倍政権を批判したいだけ
とはいえ、白井氏は「国体」じたいに端から興味がないのだろう。氏の目的は、
「ヘーゲルはどこかで、すべての偉大な世界史的な事実と世界史的人物はいわば二度現れる、と述べている。彼はこう付け加えるのを忘れた。一度目は偉大な悲劇として、二度目はみじめな笑劇として、と。」(「ルイ・ボナパルトのブリュメール18日」)
というマルクスの歴史認識に依拠し、「みじめな笑劇」たる「戦後の国体」の完成者と氏が目する安倍政権に死亡宣告を行うことなのだ。
これは、著者である白井氏に限ったことではない。カバーに歯の浮くような賛辞を寄せている内田樹・水野和夫・島薗進・保阪正康の各氏にしても、同書の編集者にしても同じ思いを有しているのだろう。
一方、 営業部門からすれば売れさえすれば内容など何でも良い。
歴史を動かした「陛下の御言葉」
ただ、末尾近くに記された以下の一節は、紛うことなき白井氏の本心を示すものと思われる。
(前略)「お言葉」は、この国の歴史に何度か刻印されている、天皇が発する、歴史の転換を画する言葉となりうるものであると、筆者は受け取った。つまり、「お言葉」は、古くは後醍醐天皇による倒幕の綸旨や、より新しくは孝明天皇による攘夷決行の命令、明治天皇による五箇条の御誓文、 そして昭和天皇の玉音放送といった系譜に連なるものである。そのような言葉を自分の耳で聞くことがあろうとは、それまで夢にも思わなかった。
この発言には、筆者も深く共感する。それゆえ、本誌平成28年9月号に掲載した「陛下のお言葉を拝し奉りて」という一文を次のように締め括ったのだ。
安倍首相が頼りにならぬのなら、一人一人の国民がそれぞれ御下問と向き合い、万世一系の天皇に関する理解を深めていくことを通じて陛下の御期待に応え奉るよりほかにない。里見日本文化学研究所・日本国体学会としても全てを擲つ覚悟である。
今上陛下の「お言葉」は今上陛下日本国の統治者たる御自覚に発せられたものであり、その大御心を国民の大半は謹んで受け入れた。それゆえ、安倍首相も御譲位を進める判断を下したのであろう。
日本国憲法との兼ね合いがあるため、国権の最高機関である国会の議決を経て皇室典範の特例法が成立するという形になったが、今上陛下の御意思を契機として現実政治が動いたという事実は動かしようがない。
今回の「お言葉」に対しては、これまで尊皇心篤いと思われていた人々(その多くは安倍政権の支持者であった)から異議申し立てがなされた。
その説くところは、歴史を踏まえ、生じ得るリスクを指摘するものであり、傾聴に値する点も少なくなかったけれども、「現在」に対する洞察と「未来」に向かっての覚悟を欠いていたように思われる。
「国体」に対する信解こそ未来を切り拓く
彼らに比して、今上陛下の「お言葉」を「歴史の転換を画する言葉」と捉えた白井氏は現在進行形の事態を正しく見通している。
白井氏はいう。
「お言葉」が歴史の転換を画するものでありうるということは、その可能性を持つということ、 言い換えれば、潜在的にそうであるにすぎない。その潜在性・可能性を現実態に転化することができるのは、民衆の力だけである。民主主義とは、その力の発動に与えられた名前である。
氏のいう通り、「現在」における潜在性・可能性を「未来」における現実態に転化できるか否かは民衆次第である。だが、その力が発動する方向性を定めるのは統治者たる天皇だけだ。そのことを、われらは決して忘れてはならぬ。
われらは、「民主主義」などに希望を抱くのではなく、天皇を戴く「国体」に対する信解を固めることを通じて、「未来」を切り拓く決意を固めねばならない。
金子宗德(かねこ・むねのり)里見日本文化学研究所所長/亜細亜大学非常勤講師
この記事は、月刊「国体文化」平成30年6月号に掲載されました。


.png)
.png)

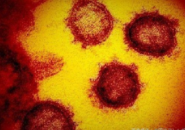








.png)
.png)
.png)




