8月22日午後、第3回浦安日本塾が開講。今回も、前回に引き続き楠公(楠木正成)が取り上げられた。
主催者の折本龍則氏(浦安市議会議員)から、前回のおさらいも兼ねて楠公の事跡に関する説明がなされた後、真木和泉の「楠子論」について学んだ。
正成は、鎌倉幕府打倒のため立ち上がった後醍醐天皇を助けた人物で、戦前は多くの人々の尊敬を受ける人物として真っ先に名前が挙げられたが、戦後は忘れ去られてしまった。正成の何が偉いのかといえば、①軍略の天才、②主君への忠義、③天皇親政を支えた人物、といった側面が挙げられる。どれも重要であるけれども、とりわけ③が重要ではないか。
後醍醐天皇は自ら「後醍醐」の諡を定められ、宇多天皇・醍醐天皇という天皇親政の時代に倣う御意志を公にされた。そして、記録所を開設された。記録所は、同じく親政を行った後三条天皇の事跡に倣ったものである。そうした後醍醐天皇の御意志に沿い奉る者が殆ど居ない中で一人立ち上がったのが、楠公であった。
後醍醐天皇の建武中興は、結果として二年弱で頓挫してしまう。これをご失政の結果と見なす見解もあるが、北畠親房が『神皇正統記』でいうように、武士が自己の欲に任せて恩賞を無尽蔵に欲しがることも崩壊の原因となったのではないか。楠公は湊川の戦いで足利勢に押されて湊川の戦いで戦死したものの、そこでも逃げようと思えば逃げることができた。しかし、それをしなかったのは後世の忠臣の模範とするためではないか、と論ずるのが真木和泉の「楠子論」だ。真木は、後世の織田信長や豊臣秀吉が皇室を廃さなかったのも楠公が忠義をみせたからだ、と述べている。〔愚泥〕

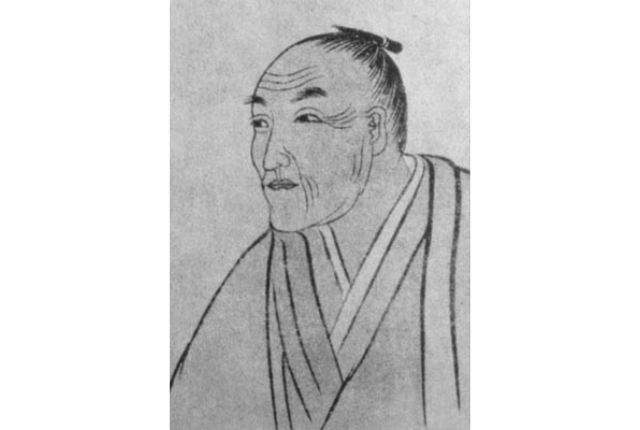
.png)
.png)

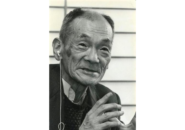

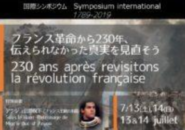






.png)
.png)
.png)




