9月22日午後、貸会議室オフィスゴコマチ(京都市)にて、民族文化研究会関西地区第17回定例研究会が開催された。
報告者は、中村龍一氏と半木糺氏。
まず、中村氏が、「福田恆存入門 ― その来歴・思想・著作」と題し、福田恆存の人物と事績を概観。福田は、英文学者として出発しつつ、政治評論・社会批評といった方面でも発言を続け、劇作家として「現代演劇協会」・「劇団昴」を主宰するなど、多彩な活動を行ったことで知られる。本報告では、こうした福田の多面的な思想を、文学論・政治論・国語論・演劇論・恋愛論・文化論といった視座から取り上げた。
続いて、半木氏が、「『西郷隆盛』はいかに受け止められたか ― 『思想家』葦津珍彦と『思想史家』先崎彰容の西郷像の比較」と題し、葦津珍彦と先崎彰容における西郷像を比較。西郷隆盛が日本近代史を把握する上での巨大な思想的存在であることを前提とし、こうした西郷をこれまでの思想史叙述が如何に受容してきたかを問うことが、本報告の課題だとされる。そこで、「思想家・運動家」の感性に基づいた西郷像と、「学者・批評家」の感性に基づいた西郷像の対比という枠組が導入され、前者として葦津珍彦による西郷論が、後者として先崎彰容による西郷論が選択され、両者の西郷像を比較するもの。
その後、里見岸雄『討論天皇』の輪読を行った。今回は、関西に来訪中の金子編集長〔民族文化研究会顧問〕も出席し、盛会だった。
(湯原静雄)
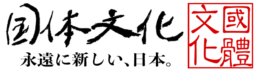

.png)
.png)





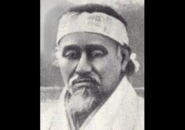

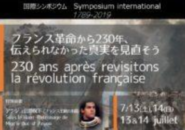




.png)
.png)
.png)




