6月1日午後、人工妊娠中絶に反対する活動を続ける〈ファチマ聖母の会・プロライフ〉主催の講演会「第3回・カトリック復興の集い」が、曙町児童会館(文京区)で開催された。
まず最初に、ビルコック神父〔ピオ十世会〕による「政治哲学・1789年の革命による政治変化」と題する講義の動画を上映。五回にわたる連続講義の第一回目にあたり、現代社会の思想的混迷についてフランスの歴史に基づいて解説。伝統的な「社会(société)」においては、家族・同業組合・国家からなる重層的な共同体の下で、正義を観想する存在としての聖職者・正義を具現化する存在としての貴族・生産活動をする存在としての第三身分(平民)とが、それぞれに恩義を受け、それぞれに義務を果たすことにより「平和」を実現していたにもかかわらず、正義に代わって権力が貴族の主たる関心事となってしまった結果、聖職者が弱まる一方で第三身分が強まり、結果として革命に繋がった。それと同時に、恩義と義理による相互の紐帯は破壊され、個人が絶対化してしまった結果、「分離社会(dissociété)」とでも呼ぶべき状況が出現した。そして、今や最も自然な共同体である家族すら解体の危機に瀕しているが、その自然性ゆゑに再興は必ずや可能であると結論づけた。
続いて、ジェーソン・モルガン氏〔麗澤大学外国語学部准教授〕が「米国南部と日本との類似性」と題して講話。アメリカのルイジアナ州ニューオリンズで生まれ、テネシー州で少年時代を過ごしたモルガン氏は、生粋の南部人として「ヤンキー」すなわち北部人に対する違和感を率直に表明する。続いて、19世紀の南北戦争における(北部が主導する)合衆国政府の南部に対する仕打ちと20世紀の大東亜戦争における合衆国政府の日本に対する仕打ちを比較し、合衆国政府が振りかざすプロテスタント的な革命主義の被害者としての共通性を指摘。その上で、南部と日本を守るためにも、合衆国政府の解体を望むと話を結んだ。
最後に、ポール・ド・ラクビビエ氏〔里見日本文化学研究所特別研究員〕が「父の使命」を題して講話。現代社会の思想的混迷は「父らしさ」の欠如に起因すると指摘した上で、カトリックの伝統的教育論において父の役割が如何に説かれてきたかを紹介した。

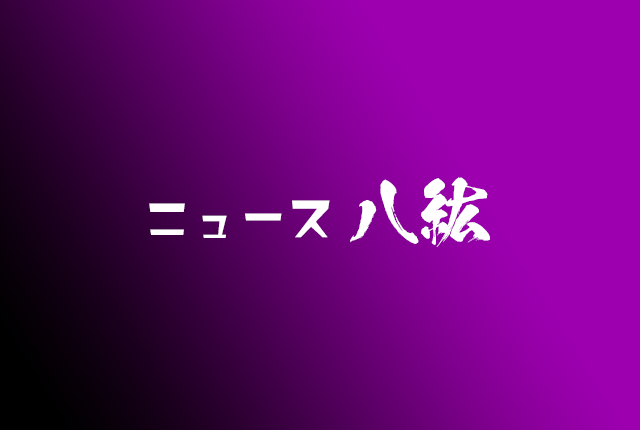
.png)
.png)











.png)
.png)
.png)




