3月16日午後、ハロー貸会議室神保町(東京都千代田区)にて、昭和12年学会第3回公開研究会が開催された。
倉山満事務局長の挨拶に引き続き、樋口恒晴氏が「昭和12年の軍事状況 ― 陸軍改革を中心に」と題して講演された。昭和12年前後の日本陸軍の体制について「日露戦争程度の戦争観で、実際には(時代の進展を考慮すれば)日露戦争未満の事態のみ対処可」と結論し、戦前日本の「軍国主義」は“ふだん不勉強な子供が試験前に必死にお守りを買って神頼みをする構図”に喩えた。加えて、戦後の陸上自衛隊の『防衛白書』の「主要各国の師団の比較」という表が昭和58年版を最後に載っていないことを指摘し、世界の大勢を等閑視する姿勢は今日に於ても変わらないと指摘した。
小休憩の後、里見日本文化学研究所客員研究員でもある宮田昌明氏が「昭和12年の日中外交史 ― 佐藤外交からトラウトマン工作まで」と題して講演された。宮田先生にとっては前日の国体文化講演会に引き続く二日連続の講演だが、支那事変を日本と支那という二つのファクターでのみ見るのでなく、圧倒的な情報量を有する事実を積み上げることで、トラウトマン(駐華ドイツ大使)による和平交渉やイギリス外交(「大国牽制=小国による大国包囲」の理念)、アメリカ外交(普遍的理念の提唱)といった様々なファクターを明らかにする宮田流の説明を今回も聞くことができた。
聴衆の関心も高く、講演の後の質疑応答では両講師に多くの質問が寄せられていた。〔田口仁〕
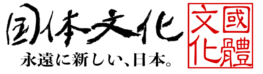

.png)
.png)



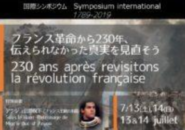
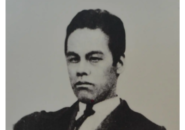



.png)
.png)
.png)




