愛知大学現代中国学部教授 樋泉克夫
◆ 「国体文化」平成28年12月号より
十月十三日、タイのチャックリー王朝ラーマ九世に当るプミポン国王が八十八歳(一九二七年~)で崩御され、タイ全土は一斉に喪に服した。喪服姿の人々が黙々と、粛々と王宮に足を運ぶ光景を、内外メディアは亡き国王の威徳を讃仰する国民の素朴な振る舞いであると伝える。だが、一面では将来に対する国民の漠然とした不安の表れとも受け取れる。
現在のタイにとっての最大の不安要因は、悲しみに暮れる国民の前に、未だに新たな国王像が示されていないことだろう。
王国・王制の安泰を求めて
現王朝を開いたチャックリー将軍は民衆の願いを受け前トンブリ王朝の混乱を鎮圧し、一七八二年にラーマ一世として王位に就いた。その後、英仏など西欧列強の東南アジア進出の渦に巻き込まれるが、明治元年に当る一八六八年に即位したラーマ五世による近代化が奏功し、王制に絶対的権威をもたらすと同時に周辺諸国とは異なり殖民地化を防いだ。
だが二十世紀に入り、王制は危機を迎える。
五世王が没した翌一九一一年には早くも民主化を求める反乱がおきた。因みに一九一〇年には日韓併合が行われ、一九一一年には辛亥革命が起り、清国が崩壊している。上海事変勃発の一九三二年には「立憲革命」が起り、専制君主制から立憲君主制へと政体は大きく変貌する。
…… ……(続きは本誌「国体文化」平成28年12月号で)

【執筆者略歴】
樋泉克夫(ひいずみ・かつお)
山梨県生まれ。香港中文大学新亜研究所で学び、外務省専門調査員(在タイ大使館)、愛知県立大学教授を経て二〇一一年より現職
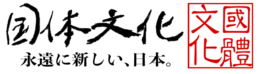

.png)
.png)
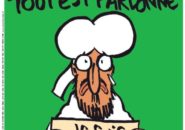









.png)
.png)
.png)




