2月23日午後、武蔵野市立かたらいの道・市民スペース〔東京都〕において、国体学講座(第6期)《「国体」とは何か?――里見岸雄と「国体科学」》が開催され、金子編集長が「『国体』の実践」と題して講義を行った。
これまでの講義を振り返り、金子編集長は里見博士の「国体」論を以下のように要約した。
- 「国体」とは、主権在所を巡る概念でも、「国柄」や「国民性」の別名でもなく、日本民族が歴史的に形成してきた「国家の一番奥底の土台となっている基本社会としての民族生命体系」である。こうした「国体」は世界各国に存在することが理論的に想定されるけれども、現存しているのは日本のみであり、それゆえに「万邦無比」である。
- 日本の「国体」とは、日本民族の天皇と国民とが、生物的基礎たる「血縁」、前者に伴って存在する「心縁」、自己統収的つながり(生命体に内在する合目的的調和・合目的々統一)たる「治縁」により、天皇と国民とが本末上下的生命体系を形成しているといふ事実そのものである。
- これらは、自己保存・拡張を目的とする生命体としての人間が、その目的を達成すべく、祖孫親子本末上下、兄弟姉妹長先幼後、同種同族遠近親疎の自覚的生命体系として共同体を形成してきた結果である。
この前提に基づき、里見博士の『科学的国体論――国体科学入門』の第六章「国体実践」を読み進める。
「日本国民は、永久に不快の印象となって消ゆることなき悲惨なる今回の敗戦の中から、祖国再建の大業に邁進するに際し、一度び、静かに歴史を回顧し、現在を凝視し、大いなる反省と厳烈なる自己批判とに徹底すべき」と主張する里見博士は、生命体系としての国体と生活体系としての政治経済機構との関係についての法則を科学的に確認するに到らなかったため問題を生じてきた事実を真正面から見据え、「天皇と時代社会の階級的権力とを徹底的に分離し、天皇をして、飽く迄、民族生命体系の中枢として、日本という国家の内在的とを弁証法的に統一し得る地位に安坐せしめ奉る工夫を為し、然る上、改めて、いかにせば階級社会の矛盾を永遠除去し得るかを、しばらくも停止する事なき闘争事実のさなかに研究する道を講ずべき」(一五七頁)と主張している。
また、里見博士は「日本が今後生きてゆく方途は、飽く迄道義的平和国家、人間発展の頂点としての文化国家の建設以外にない。然し、その事は、決して、単なる道義的観念や平和観念をお題目として唱える国家になることではなく、事実に於て、まず日本が世界各国から模範として仰がれる尊厳なる道義的生活を行う国家となることでなければならぬ」(一五九頁)として、道義的生活を実現するために幾つかの提案を行い、同書を締め括っている。
そうした里見博士の問題提起を踏まえ、金子編集長が「新時代における『国体』論と実践」の方向性について展望を語った。生産力の増大と交通手段および情報・通信技術の発展は社会に大きな変化をもたらしたけれども、これは不可逆的変化として受け入れるより外ない。ただ、そうした動きが人間存在の根底をなしてきた家族という「血縁」や民族や宗教という「心縁」を否定したならば、個々人に分断された世界は混乱に陥るに違いない。私たちは、日本の「国体」を手掛かりとして、里見博士の示した「異族人類同胞一体」の人類的生命体系という境地を目指さなければならないと結んだ。〔M・K〕
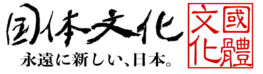
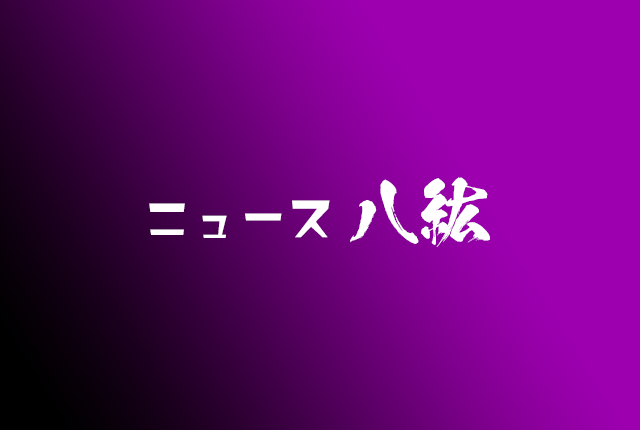
.png)
.png)


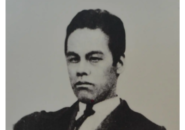
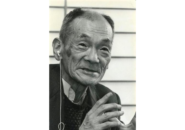


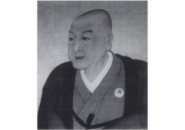



.png)
.png)
.png)




