7月18日(土)午後、貸会議室オフィスゴコマチ(京都市)で、民族文化研究会の関西地区第26回定例研究会が開催された。
報告者は竹見靖秋氏と湯原。
まず、竹見氏が、「明治初期における淘宮術結社と神祇行政」と題し、修養術の一種である「淘宮術」の結社の沿革を、それに大きな影響を与えた明治期の宗教行政を基本的な視座として概観した。
「淘宮術」は、江戸幕府の御家人だった横山丸三(写真)が創始したもので、中国由来の占術を改良し、修養術として確立した。自身の性格や特質を把握し、欠点を矯正することで、幸福な人生を送れると説く。
しかし、幕府側は、修養術と看做さず、新宗教の一種として警戒し、門弟の教育や集会の開催を禁止した。他方で、明治維新後は、諸宗教が合同で国民教化にあたる大教宣布運動に参加し、教導職にも任命された。
こうした「淘宮術」結社の沿革は各時代の宗教政策を反映したものであり、また「修養」運動と「宗教」運動の複雑な交錯を示しており、極めて興味深いものだとされる。
続いて、湯原が、「近世期における神道神学の展開 ― 中野裕三『国学者の神信仰』を読む(第四回)」と題し、第三編「鈴木重胤の神信仰」を精読することで、国学者の神道思想の現代的意義を検討した。
現在の重胤研究は、重胤の学説の個別的検討が中心で、重胤国学の全体像の把握や具体的な思想分析が疎かになっている。本章では、重胤の神道思想の特色が最も表れている祭祀論に焦点を絞り、また平田篤胤からの影響など形成過程を跡付け、その実像に迫っている。(湯原静雄)
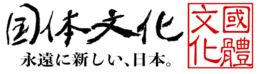
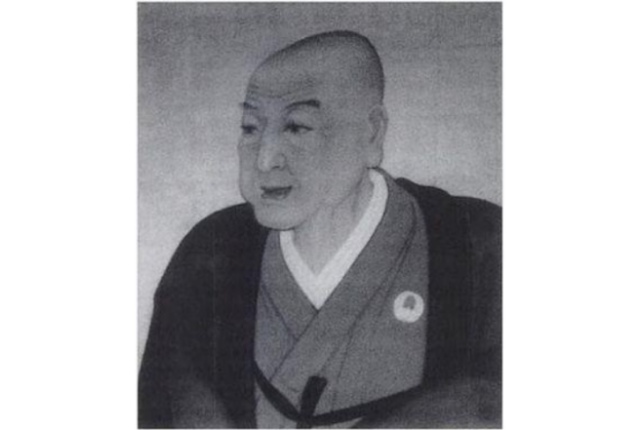
.png)
.png)








.png)
.png)
.png)




