即位礼正殿の儀に用いられた高御座・御帳台などの特別公開(主催…内閣府・宮内庁・東京国立博物館)が、12月22日から1月19日にかけて上野の東京国立博物館・本館で行われた。
第1会場に入ると、手前に高御座、奥に御帳台が安置されていた。高御座・御帳台ともに朱塗りの高欄を巡らせた黒漆塗りの方形の基壇の上に八角形の床板が置かれ、八本の柱が八角形の蓋(屋根)を支える造りであり、「八紘一宇」の語を想起させる。
天皇が即位に際して高御座に立たれるようになったのは、遅くとも平安時代初頭から。『日本書紀』には雄略天皇の即位に際して「壇(たかみくら)」が設けられたという記事があり、その始原は古墳時代にまで遡ると見てよいだろう。一方の御帳台は、皇后の御座として近代に入ってから用いられるようになったもの。
なお、今回の御代がわりにおいて用いられた高御座・御帳台は大正天皇の御即位に際して謹製されたものだが、百年前以上前のものとは思えない輝きを放っていた。
第2会場では、正殿の儀にて用いられた装束が展示されていた。
会場の国立博物館によれば、20日間で20万人が拝観したとのこと。国民の高い関心が窺われる。
なお、高御座・御帳台は京都御所に戻され、そちらでも3月1日から22日まで特別公開が行われる(主催…内閣府・宮内庁)ので、近在の方は是非とも拝観されたい。〔東山邦守〕


.png)
.png)


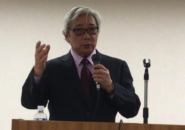






.png)
.png)
.png)




