12月26日、政府はIWCからの脱退と翌年7月からの商業捕鯨再開を決定した。

IWC脱退を発表する菅義偉官房長官
IWCは国際捕鯨取締条約に基づき鯨資源の保存及び捕鯨産業の秩序ある発展を図ることを目的として設立された国際機関であるが、鯨油の代替品が開発されたことに伴い、それまで乱獲の限りを尽くしてきた欧米諸国が鯨の保護を主張して捕鯨反対に転じ、主として鯨肉を確保するために商業捕鯨を続けようとする我が国などに圧力を加えるようになった。
商業捕鯨の継続を断念した我が国は科学調査を目的とする捕鯨に切り替えて捕鯨の継続を図る一方、捕鯨に反対する欧米諸国や豪州などとの合意を目指してきたが、IWCの枠内における捕鯨の継続は困難と判断したのだろう。食料自給率の低い我が国にとって領海や排他的経済水域で捕獲される鯨は貴重な食料資源であり、世界人口が増加し、食料の需給バランスが崩れる可能性も否定できない中、その活用を図ることは国家安全保障の観点からも重要だ。
調査捕鯨は南氷洋(南極海)の公海上で行われていたために自然保護団体の船舶による妨害を受けてきたが、今後は我が国の領海および排他的経済水域内において行うために妨害を受けることもなくなる。もちろん、課題も多い。IWCを脱退したからと云って、鯨を保護する義務を負わずにすむわけではない。捕鯨に反対する諸国を納得せしめるためにも徹底した調査が必要だ。また、捕鯨を継続している他の国々とも連帯する必要があろう。ノルウェーを中心とするNAMMCO(北大西洋海産哺乳動物委員会)に加盟するという方法もある。

古式捕鯨
それ以上に重要なのは、鯨食文化の再興だ。「くじら」の語は『古事記』や『日本書紀』に見られ、『万葉集』には捕鯨を意味する「いさなとり」の語も登場するなど、鯨食文化の歴史は古い。けれども、昭和三十年代には年間二十万トンを超えた鯨の消費量は今や年間数千トンに減った。かつては学校給食の定番メニューだった鯨料理だが、今日では珍味の類である。
捕鯨が産業として成立するためには、一般的な食材として国民に認知されねばならない。学校給食の記憶と結びついて鯨肉を敬遠する層や鯨肉を食べ慣れていない若年層に鯨食の魅力を伝える必要があろう。〔M・K〕
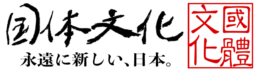
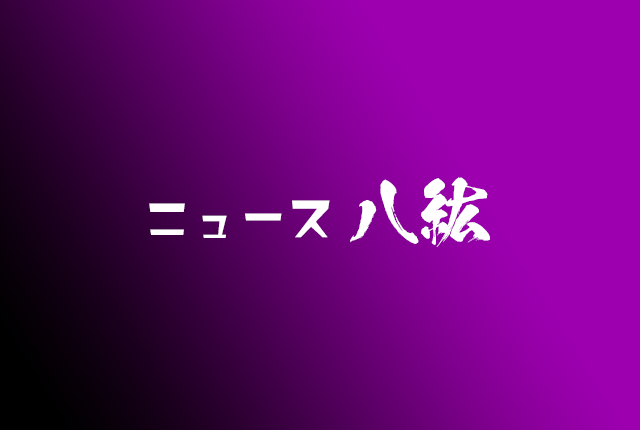
.png)
.png)
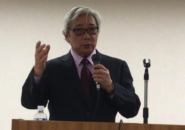





.png)
.png)
.png)




