11月11日午後、ベルサール神田(東京都千代田区)で《昭和12年学会》第1回研究発表大会が開催された。
同学会は、会長・宮脇淳子氏(東洋史家)、事務局長・倉山満氏(憲政史研究者)、大会準備委員長・藤岡信勝(教育研究者)の3名が中心となり、5月28日に設立された。専門分野の異なる研究者が、「昭和12年」を切り口としてイデオロギーと専門分野の枠組みを越えて議論・研究を行っていくという。
実際、第1回大会の発表には様々な専門分野とキャリアを持つ研究者が集い、学会の目指す方向性をしっかりと打ち出すものとなった。
最初に登壇したのは会長の宮脇氏。会長講演として「昭和12年学会とは何か」を演題に講演を行った。これは大会の基調講演であると同時に、学会設立の決意表明の役割を果たし、学会の船出を強くアピールするものであった。
この後は三つのセッションに区切られ、セッションごとに司会者が取り仕切る形式で進められた。
倉山氏が司会を務めた第1セッションでは、本誌に『歴史と今後を見つめる』を連載中の宮田昌明氏〔一燈園資料館「香倉院」勤務〕による「昭和12年の日中外交史―佐藤外交からトラウトマン工作まで」、小野義典氏〔城西大学准教授〕による「支那事変の国際法的考察」、小山常実氏〔大月短期大学名誉教授〕による「戦時国際法の『交戦者資格』と日中戦争期の中国軍―通州事件の検証を通して」という、昭和12年最大の事件とも言うべき支那事変を中心軸に据えた発表がなされた。この第1セッションにおける発表を聞いた聴衆は、この学会が政治運動体ではなく、学術団体を志向するものであるということを改めて感じたであろう。

講演する宮田昌明氏
続く第2セッションは中世軍事史を専門とする海上知明氏〔日本経済大学教授〕が司会を務め、内藤陽介氏〔郵便学者〕による「昭和切手の発行」、樋口恒晴氏〔常磐大学教授〕による「昭和十二年の軍事状況」、柏原竜一氏〔情報史家〕による「一九三七年のインテリジェンス」の3つの発表が行われた。このセッションでは、昭和12年における我が国の切手・陸軍・情報機関を取り巻く情況が解説され、「昭和12年とはいかなる時代であったのか」について理解を深めるものとなった。
最後の第3セッションは、藤岡氏が司会を務め、緒方哲也氏〔東京国際大学専任講師〕による「通州事件と阿片問題―通州事件が引き起こされたのは阿片が引き金なのか?」、峯崎恭輔氏〔放送大学学生〕による「正定事件と在支カトリック情勢―田口枢機卿の北支視察より」、樋泉克夫氏〔愛知県立大学名誉教授〕による「P・バックと昭和十二年前後の日米中を巡るソフトパワー―『大地』と『中国=文化と思想』を巡って」、高木桂蔵氏〔静岡県立大学名誉教授〕による「日本における中国史研究の特色」の4つの発表が行われた。このセッションは、前の二つと比べて発表者のキャリア並びにテーマも幅広いものとなったが、日本人が大陸で対峙することになった支那および支那人とは如何なるものであったのかを改めて探る機会になったと言えよう。
参加者には若年層の姿も多く、新しいものが始まるという高揚感に包まれた大会となった。今後の昭和十二年学会の活動が、旧態依然とした歴史学界に一石を投じるものとなることを期待したい。〔H・K〕
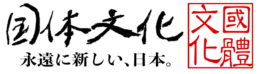

.png)
.png)
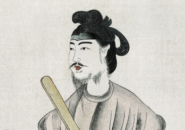
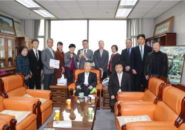



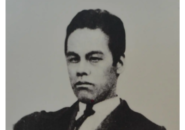





.png)
.png)
.png)




