6月20日(土)午後、貸会議室オフィ スゴコマチ(京都市)で、民族文化研究会関西地区第25回定例研究会が開催された。緊急事態宣言が解除されたことを受け、今回の研究会から通常の会場での開催に切り替えた。
報告者は中村龍一氏と湯原。
まず、中村氏が、「京都御所と近代京都のつながり ― 令和時代の御所の在り方を探して」と題し、近代以降の京都御所の沿革を概観した。京都御所は、時代 によって異なる空間へと変遷しつつ、その在り方が京都市民にも大きな影響を与え、京都という都市の方向性そのものを規定してきた。
たとえば、明治期における御所の保存と御苑の整備が、東京遷都によって衰退していた京都市街の再整備に繋がった。また、大正期には、即位礼・大礼奉祝行事を契機に、御所・御苑の公開性が高まり、大正デモクラシーの影響もあり、市民の自由な空間を京都市街において出現 させた。
本報告では、こうした京都御所と京都市街のつながりを踏まえ、その歴史的沿革を概観することで、令和時代における御所の在り方と、京都という都市の将来を考察する。現在の単なる文化財・公園という御所・御苑の在り方にとどまらず、御所・御苑を国民精神を涵養する場へと転換させ、それを京都の地域振興へと繋げることが提案された。
続いて、湯原が、「近世期における神道神学の展開 ― 中野裕三『国学者の神信仰』を読む(第3回)」と題し、中野裕三『国学者の神信仰』を精読することで、国学者の神道思想の現代的意義を検討した。前回は第一編「本居宣長の神信仰」を紹介したが、今回は第二編「橘守部の神信仰」を検討する。
この章では、従来の橘守部研究の課題を踏まえ、守部の神道思想が概観される。 宣長批判者として知られる守部の神道思想を検討することで、宣長の神道思想がいかに継承・克服されたかを知ることができる。しかし、村岡典嗣・加藤玄智による戦前期の守部研究は、守部の神道思想の全体像を把握せず、表層的な解釈にとどまっていた。本章では、文献学的なアプローチも援用し、守部の神道思想の発展過程を明らかにし、宣長から受けた影響を分析した。〔湯原静雄〕

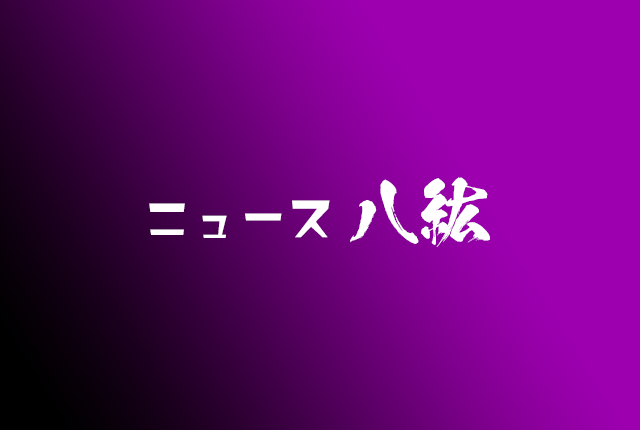
.png)
.png)
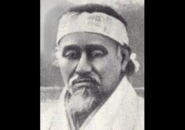




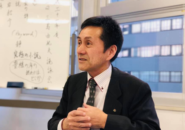






.png)
.png)
.png)




