1月17日、ポール・ド・ラクビビエ氏(里見日本文化学研究所特別研究員)を講師に「現代の日本とカトリック」と題した講演会を、合同会社宗教問題の主催で行いました。同社で発行します季刊『宗教問題』の「読者の集い」として開催したものです。
昨年11月発行の『宗教問題』誌二十八号では、「ローマ教皇38年ぶり来日の意味」という小特集を組み、ポール氏のほか、(中曽根康弘平和研究所研究顧問)南條俊二氏、広野真嗣氏(ノンフィクション作家)に寄稿を依頼しました。いまなお日本人の記憶に新しい、同月のローマ教皇フランシスコ来日の意義に関して、それぞれの思いを開陳してもらったものです。その特集の関連行事として、ラクビビエ氏の講演会を編集部として企画しました。
さて、『宗教問題』28号にての小特集の内容は各自で参照していただくのが一番ですが、ラクビビエ氏の論考に関してかいつまんで説明しますと、ます同氏は自身がカトリック信徒であることを明かしたうえで、「信仰者」とはまず教義を尊重し、それに基づいた生活を送ることこそが肝要だと説きます。そして現在のカトリック組織とは、それとは直接関係がない政治的な活動が多すぎるとし、その組織的堕落を批判。教皇の来日もそれ自体は喜ばしいことだが、恐らく政治的言動が多くなるだろうと予測し(実際にそういう流れになりました)、「具体的な“成果”のようなものは特に期待していない」と締めるものでした。
いかがでしょうか。あまり現在の日本の論壇の中では聞くことのできない論説で、雑誌発行後、編集部にはこのラクビビエ氏の論考に関して賛否両論、さまざまな反響が寄せられました。「信仰者としての芯が通っていて素晴らしい」というものから、(ラクビビエ氏には失礼でしょうが)「狂信的だ」というような非難もありました。そういう流れを経ての、ラクビビエ氏講演会でした。
講演会とは、やはり現場で講師の言葉に耳を傾けた方の“心にしみ込んだもの”が一番の財産だと思います。ですから私もここで、ラクビビエ氏の講演内容を一言一句再現するような野暮はしません。しかし、小さい会場ながらほぼ満員の20人超を前に始まったラクビビエ氏の講演は、冒頭から寄稿と同様に非常に刺激的なものでした。
「近代ヨーロッパとカトリックは宿敵です」
ラクビビエ氏はまずそう言い、「中世」の主役であったカトリックと、「近代」をけん引したプロテスタントを対比し、後者のその欺瞞性を衝きます。そして、キリスト教の根幹とはよく知られるように「愛」です。その愛を突き詰めて(あえて誤解を恐れず書けば「原理主義」的に)解釈すると、同性愛、人工中絶、そういうものは元来許されない事柄であり、ラクビビエ氏もそうハッキリと断言します。それを受け入れている現在の欧米の社会には、おかしなものがあるとも。
ラクビビエ氏は保守の立場に立つ者だと、ご自身でも規定します。ただ、同氏の保守的精神は、以上のような強いカトリックの精神に支えられていることに着目する必要があります。日本でも「自分は保守、右派である」と語る人は多数います。しかし、その精神はいったい何に裏付けられているのでしょうか。たとえば中韓や、国内左派勢力への「カウンター」的な考えだけで、そう言っている人も少なくないのではないでしょうか。私は今回のラクビビエ氏の講演を聞いて、(それは決してキリスト教でなくともいいのですが)保守、右派の精神の背景には何らかの「信心」が必要なのではないかということを、強く感じました。
特に、同性愛や人工中絶を一方的に断罪するというのは、現代の日本人にとって「保守」であっても、容易に受け入れられない考え方かもしれません。しかし、「神の愛」とともにそれを説くラクビビエ氏の姿は本当に堂々としていて、一分のスキもないように見えました。これが「信じる者の力」です。信条、立場を問わず、一つの主義を奉じて進む人間とは、本当にかくありたいものです。
またラクビビエ氏は、日本は古来より神道的考え方を重視してきた国であり、その意味で古い伝統に立脚するカトリック世界とは親和性、共通性があると指摘。一部で言われる「日本の国柄にキリスト教はなじまない」という考え方には疑問があるとも語りました。かくなる論者がいま日本で生活しておられることは、日本人として喜ばしいことです。これからもラクビビエ氏には、本邦において大いに論客として活躍していっていただきたいと思います。
講演終了後の質疑応答において、客席におられたイスラム教徒の方から、質問の挙手がありました。その方はリベラルで、詳細は記しませんが、ラクビビエ氏とかなりの丁々発止を演じておられました。ただ、その方は後日、『宗教問題』編集部に「ラクビビエさんとの出会いに感謝します。口はばったいようですが、やはり信仰を貫く人には相通ずるものを感じました」というメールを送ってこられました。何とも感動的ではありませんか。繰り返しますが、これこそ「信じる者の力」です。私も宗教専門誌を発行する立場として、今回のラクビビエ氏講演会からいただいた感動を、ずっと忘れず憶えていたいと感じました。〔季刊『宗教問題』編集長・小川寛大〕
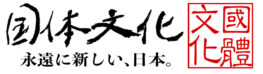

.png)
.png)










.png)
.png)
.png)




