皇太子殿下が新帝として即位された後、国内の行幸に際して飛行機や列車の貸切りを止めることが検討されていると、12月15日に日本テレビが報じた。
昭和の御代においては、原宿駅近くに設けられている宮廷専用ホームから御料車などを連結した御召し列車が運転されていた。発車や停止に際して衝撃を生ぜしめないことはもちろん、運転時刻や停止位置などにも通常以上の正確さが求められ、運行にあたる運転士は技能のみならず人間性においても優れた者が選ばれたという。また、車両の整備に際しても細心の注意が払われた。
昭和天皇の御乗車されていた御料車が老朽化したため、JR東日本は平成20年に新しい御料車(E655系)を新製したものの、あまり運行されてこなかった。新幹線や飛行機で行幸されることが一般的となり、在来線に御乗車あそばされる機会じたいが減ったためだが、通常の車輌や機体を貸切りにする場合でも、運行や整備には細心の注意が払われてきたものと思われる。
報道によれば、殿下は費用のことを御懸念あそばされているらしいとのこと。大嘗祭に関する文仁親王殿下の御発言と同じく、国民を慮られての御発想と拝し奉るが、一般客の同乗を許すと却って警備費用が嵩むのではないか。また、天皇陛下が御乗車される車輌、あるいは御搭乗される機体の運行や整備に携わる者は、神経を使うかもしれぬが同時に誇らしさを感じているという。また、そうした特別な列車や飛行機を間近で拝することもまた得難い経験である。
12月17日、宮内庁の西村康彦次長は、定例記者会見において、貸切りを止めることを検討したことを認めた上で、警備上の都合やJRからの要望を踏まえて従来通りの形態を維持し、上皇および上皇后の行幸啓においても同様の形態を採用する方針を明らかにした。
結果としては収まるべきところに収まったものの、皇室としての品位を保つべく必要な費用さえ削ろうとする動きが再び起こらぬよう、今後とも注視していきたい。〔M・K〕
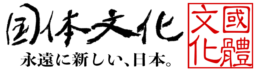

.png)
.png)



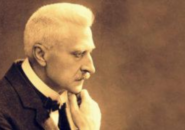






.png)
.png)
.png)




