
筒井清忠 編『昭和史講義――最新研究で見る戦争への道』
戦後七十年を機に、昭和史に対する関心が高まり、様々な新刊書が書店に並んでいる。だが、その多くはイデオロギーと予断に満ちており、手に取ろうという気にならない。
そうした現状に対し、広範囲な昭和史研究において「専門の研究者は、専門研究に特化し研究者同士が少し時期が違うとお互いの成果を知らないというのが実情(8p)」であるとする編者の筒井清忠(帝京大学文学部長兼教授)が主導する形で、最新研究のガイドブックを目指して本書が作られたのだという。
編者の筒井は丸山眞男批判や二・二六事件研究で知られるが、本書においても、それぞれの執筆者が実証的な手法で昭和史に迫っている。
しかし、専門を少し離れると、乱暴な表現も見える。たとえば政治外交史を専攻する等松春夫は、「第5講・満州事変から国際連盟脱退へ」において石原莞爾の戦争思想を論じる中で「日蓮宗系宗教団体である国柱会(94p)」と表現しているが、国柱会は「日蓮宗」の分派ではない。ここは「日蓮主義を奉じる在家仏教教団」とでも表記するのが正しいだろう。これに限らず、政治外交史ばかりで思想史に関する目配りが薄いことが気になった。
面白い点が一つある。宮田昌明の『英米世界秩序と東アジアにおける日本』に関して、「緻密な実証研究」「厳密な史料批判」「例外的に優れた研究」と評価しながらも「ややオーバーと思われる表現もある」「やや行き過ぎが感じられる箇所がないではない」とコメントを付して執筆者の各氏が紹介している。刊行から日が浅い中、現在の通説を徹底的に検証した大著を多くの研究者が参考文献として評価したことは歓迎すべきことだが、アカデミーにおける世渡りのためか姿勢が及び腰なのは頂けない。非常に残念ではあるが、宮田書の意義を逆説的に証明する形となった。
何はともあれ、このような書籍が新書という形で出版されたことは意義深いと言えよう。才ある若き執筆者に期待したい。(和)
筒井清忠 編『昭和史講義――最新研究で見る戦争への道』
▼筑摩書房(ちくま新書1136)
▼平成27年7月10日発売
▼本体価格 八八〇円
▼ISBN 978-4-480-06844-6
(「国体文化」平成27年9月号所収)
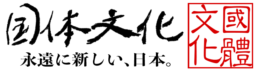

.png)
.png)






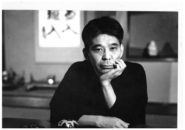
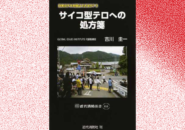





.png)
.png)
.png)




